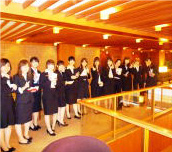| 宮崎ゼミの学生の活動 |
| 株式会社ファンケルの小倉さんから同社のCSRについてご講演いただきました。 12月19日、「地球環境と私たちの生活」をテーマする宮崎ゼミでは、株式会社ファンケルCSR推進事務局の小倉さんからCSRについて講演していただきました。 講演では、同社の従業員が家族とともに取組む家庭での省エネ努力に対し報奨金を出しており、環境大臣賞を受賞したことが紹介されました。 講演後は質疑応答の後、社会的な課題に対して同社と大学生が協力して取り組み具体鉄器なアイデアについて学生が3グループに分かれて討議し、その結果を発表しました。 |
 |
| 入学前オリエンテーションの学科プログラムで宮崎ゼミ生がプレゼンテ―ションをしました。 12月7日、来年度入学が決定した高校生を対象とした生活環境マネジメント学科の学科プログラムが新座キャンパスで開催されました。 合格した皆さん、おめでとうございました。 このプログラムでは、最初に学科主任である石渡先生が学科概要を説明した後、宮崎ゼミ(2年生)の4名がゼミ活動とインターンシップの経験についてプレゼンテーションをしました。 |
 |
宮崎ゼミの3年生がマネジメント学部発表会に参加しました。
|
 |
| 宮崎ゼミが日本経済研究センター主催のGSR学生コンテストに参加しました。 生活環境マネジメント学科の宮崎ゼミ(3・4年生)は、9月28日電通ホールにて開催された日本経済研究センター主催の第4回GSR学生アイデアコンテスト(注)に参加しました。発表テーマは「中国での食事と健康についての教育」です。これは、経済発展している中国で急増する小児肥満の対策としてベネッセ(教育)と第一三共(医薬品)が協働で行う新しい教育・医療ビジネスを提案するものです。 |
1.jpg) |
この発表の様子は下記のUSTREAMで見ることができます。
http://www.ustream.tv/recorded/39310228
(宮崎ゼミの発表は、00:13:18から33:08までです。)
(注)GSR学生アイデアコンテスト:大学生が企業と共に考えるGSR(=Global Social Responsibility)、地球規模での社会的責任とは--。
貧困、環境問題などを企業の力で解決する道はあるか、学生がアイデアを競うコンテストも今年で4回目。全国から選ばれた9大学のチームが、参加8企業の中から選んだ2社のリソースを組み合わせて地球規模の課題を解決するための事業プランを提案するものです。
【発表の概要】
テーマ:「中国での食と健康についての教育」
現在、世界ではストレスや食習慣などから引き起こされる心臓病、ガン、糖尿病等の「非感染症」が死亡原因の約60%を占めている。
これは先進国だけでなく、中国等の新興国でも大きな問題となっている。中国では、急速な経済成長を遂げている一方で、就労者の増加に伴い、一般的な家庭では両親が共働きのため、子育ては祖父母が担っている。また、食や健康に関する知識が十分でないため、祖父母なその子供たちにはファーストフードを与えがちであり、その結果小児肥満が急増している。
そこで、第一三共と、ベネッセコーポレーションの協力による中国での肥満対策ビジネスを検討した。このビジネスは以下の3つのステップで実施する。
一つ目は食と健康を教育さうるための教材を作成する。中国には、ベネッセが発行する「こどもちゃれんじ」という親子向け通信教育に参加する約50万人の会員がいるが、これらの会員が本ビジネスの最初の対象となる。この「こどもちゃれんじ」の追加教材として、食と健康に関する教材を付けて販売する。この教材を読んだ子供も両親も、自分が肥満なのかどうか、確かめたくなるはずである。
二つ目は肥満検診である。これは上記の追加教材の購読者には無料で受けることができるようにする。この検診の費用は、第一三共が資金し、場所としては、両社がビジネスの拠点を有する上海にて開始する。この肥満検診を受け、良くない結果が出た人に必要なものは病院へ行くことである。
三つ目は、第一三共の上海子会社に「お客様コールセンター」を設けることである。肥満検診を受けた人には、コールセンターに電話することを勧める。ここに電話をすると、近くのおすすめの病院を紹介する。中国では病院に関する情報が不足しているため、この情報は貴重なものである。このように病院を紹介されたお客さんは実際にその病院へ行く。すると、そこで診察を受けて薬が処方される。このビジネスでは、第一三共は病院をするので、病院とのコミュニケーションが増えることになる。それによって第一三共は病院との関係ができて、その結果同社の薬の販売増につながる。このようなメリットがあるので、肥満検診とコールセンターの運営資金は負担しても長期的には利益が出るビジネスになりと考えられる。
本コンテストでは提案するビジネスプランの採算性の検討が求められる。このため、このプランには、どれほどの数の中国人が関与し、どの程度の売上高の増加になるかについて試算した。また、実際に中国でビジネスとして実施する場合には必要となる課題(中国国内で出版物を販売するためのパートナーを見つける必要があること)の解決が今後の課題であることを指摘した。
最後に、両社が協働してこのビジネスを実施することによって、中国の肥満人口の減少に貢献すると結論付けた。
発表後の企業担当者からのコメント
【第一三共】
今回の発表は、グローバルな社会貢献として、3つの視点で見た。一つ目は対象国をよく理解しているか、2つ目は異業種間の企業のコラボがうまくいくか、3つ目は社会課題を的確に捉え得て、解決策を提案しているか、という点であった。まず、一つ目は中国という新興国の富裕層の肥満を取り上げ、その文化と医療の制度を良く把握していた。2つ目は、第一三共の医療とベネッセの教育の二つの領域を良くとらえている。3つ目は、新興国の社会課題として貧困の次の課題をよく捉えた。事業の採算性の試算としては、考え方としてのスキームはよく整理されている。実際に製薬企業がビジネスを開始するために医療関係者との関係を精査する必要があるが、今回の提案は企業にとっては大きなヒントになった。
【ベネッセ】
宮崎ゼミは最初違ったテーマで検討しようとして、かなり悩んでいたが、このテーマに変えてからは追い込みがすごく、多くの情報を調べてまとめ上げたことには感心した。経済発展している国の非感染症に目の付けたことが面白いと感じた。海外でビジネスを開始する場合には最初に顧客との接点を作ることが難しい点であるが、今回の発表では、弊社の発行する「こどもチャレンジ」の顧客に定め、それをビジネスプランにつなげたのは、よくまとめたなと感じた。実際に中国でビジネスするのは種々の問題があって難しいが、この困難な点をさらに詰めるとさらに面白い提案になると思う。
【参加した学生の感想】
世界で起きている様々な問題を解決するため、2つの企業の強みを組み合わせて新しいビジネスを作り、解決を試みよう!というGSR学生コンテストに参加しました。
私はチームリーダーを務めましたが、振り返ってみればこの4ケ月という間は、様々な
これもまた、当たり前のように聞えるかもしれませんが、チームメイトー人ひとりに持
また、協力してくださった2社、第一三共さんとベネッセコーポレーションさんは、訪問
今は本当に清々しい気持ちです。きっと、これからの人生で起こる様々な困難も、このようにして頑張っていけば乗り越えられると思います。最後まで頑張り抜く根性と、チームで協力しあうことや、お互い
11月4日(日)の学園祭「紫祭」では、宮崎ゼミは、チョコバナナを作って販売しました。
バナナを切って、串に刺します。 |
串刺しにしたバナナにチョコレートをつけます |
チョコバナナをグランウドで販売し、完売しました |
||
 |
 |
 |
たくさんの皆さんに買いに来ていただきました。ありがとうございました。
| インターンシップの報告(2010年度、共用品推進機構) |
2010年8月9~20日の10日間、生活環境マネジメント学科2年生の3人は共用品推進機構でインターンシップを実施しました。その内容は以下の通りです。
1つ目は、国立科学博物館の主催で13~15日に開催された「夏休みサイエンススクェア」、もう1つは経済産業省で18~19日に開催された「子ども霞ヶ関見学デー」。いずれも、夏休み中の子どもたち向けの教育イベントです。
「夏休みサイエンススクェア」は同機構が一昨年より参加しているイベントで、子どもたちに、共用品の工夫や障害のある人の不便さなどを伝え、レーズライター(表面作図器)を使って「触って分かる絵」を作ってもらうという内容です。今年は1日4回・都合12回の講座を学生3名と共に実施し、3日間で126人の子どもたちが参加してくれました。
一方の「子ども霞ヶ関見学デー」では、「標準ってなんだろう?~くらしのなかのJISと計量~」のブースで、規格化された共用品の紹介を行いました。来場した子どもたちは、保護者と一緒にシャンプー容器や牛乳パック、ラップフィルムなどの「決まり」を見つけるなど、標準の大切さを学びました。
【共用品にたくさん触れた10日間 高橋里依】
今まで、この製品には点字が付いている、これは使っていて便利なものだと感じたことはあっても、それが何のためのものなのかあまり深くは考えていませんでした。しかし、共用品推進機構でインターンシップをさせていただき、身の周りにはたくさんの共用品があり、その製品の意味、特にどんな人にとって便利なものなのかなど詳しく知ることができました。
科博のイベントに参加させていただき、子どもが好きで「将来どこかで子どもに携わる仕事がしたい」と考えていたので、とても貴重な体験になりました。共用品のことを少し知っている子、全然知らない子、さまざまでしたが、将来どこかで共用品に触れたとき、「これはこんな製品だったな」と思い出してくれたらうれしく思います。
【共用品に囲まれた10日間 近藤捺美】
共用品推進機構でのインターンシップは、私にとって初めての経験だらけでした。
はじめはイベントの準備などをし、その後、科学博物館と経済産業省での2回にわたるイベントに参加しました。最初の準備は根詰めで1週間まるまる出勤しなければならず、途中で体調を崩してしまったりもしましたが、子ども相手にどのように説明すれば分かってもらえるのか、1つひとつ考えながら話すことで言葉の難しさを学び、そのためには共用品について詳しく知っておく必要もあり、私たち自身、身近にある様々な共用品についてたくさんのことを知りました。
学んだことはとても多く、今回得た経験をこれからの人生にどう役立てていくのかを考えながら、残り半分の学生生活を有意義に過ごしていきたいと思います。
【大収穫のインターンシップ 小泉知世】
今回のインターンシップで、今まで知らなかった共用品という言葉を知り、実物を見て、触ることにより、私たちが日常生活で使用する多くのものがみんなに使いやすいよう工夫されている共用品であると知りました。
国立科学博物館では、子どもたちに共用品についてと、手で触ってわかる絵の書き方を説明させていただきました。人の前で話すことが苦手な私にとってはとても大変で緊張しましたが、静かに聞き、一生懸命問い掛けに答えようとしてくれる子どもたちに助けられ、無事終えることができました。そして、人に教えることの難しさ、相手の表情を読み取りながら話を進めていくことの重要性などを考え、実践することができました。
この10日間でたくさん経験し学んだことを、今後活かしていきたいと思います。
(インクル 第68号より)

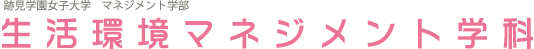
.gif)